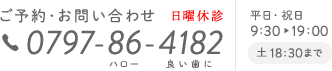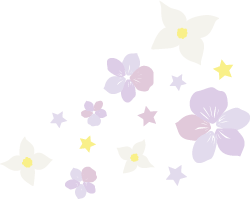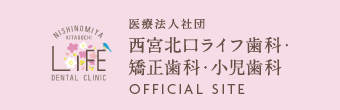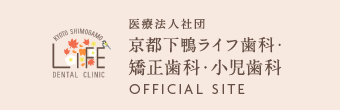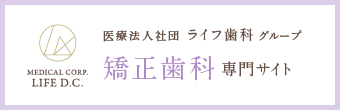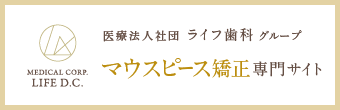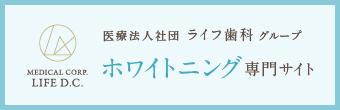こんにちは。兵庫県宝塚市にある医療法人社団 宝塚ライフ歯科・矯正歯科です。
子どもの歯ぐきが赤く腫れていたり、歯磨きの際に出血があったりする場合、歯肉炎のサインかもしれません。歯肉炎は大人の問題と思われることが多いですが、実は子どもにも起こりうる身近な口腔トラブルです。
初期の段階では痛みが少なく見過ごされやすいため、気づかないうちに進行することもあります。放置すれば将来の歯の健康に大きな影響を与える可能性があるため、早めの対処が重要です。
今回は、子どもの歯肉炎の種類やリスク、適切な対処法や予防法についてわかりやすく解説します。
目次
歯肉炎とは
歯肉炎とは、歯ぐきに炎症が起こる状態を指し、歯周病の初期段階として知られています。主な原因は歯と歯ぐきの間にたまったプラーク(歯垢)に含まれる細菌で、これが歯ぐきを刺激し、赤みや腫れ、出血といった症状を引き起こします。
特に、歯磨きが不十分な場合や、間食が多い生活を続けていると、プラークが蓄積しやすくなり、歯肉炎を発症しやすくなります。痛みがないことも多く、気づかないうちに進行するのが特徴です。
放置すると、歯を支える組織が破壊される歯周病へと進行するリスクがあるため、早期の対処と予防が重要です。
子どもの歯肉炎の種類
子どもに見られる歯肉炎にはいくつかの種類があり、それぞれ原因や症状に違いがあります。
不潔性歯肉炎
不潔性歯肉炎は、歯みがきの不足や磨き残しなどによって、歯や歯肉の周囲にプラーク(歯垢)がたまり、炎症を引き起こす種類です。子どもの場合、歯みがきの習慣が未熟であったり、正しい磨き方が身についていないことから、歯と歯ぐきの境目にプラークが残りやすくなります。
その結果、歯肉が赤く腫れたり、歯みがきの際に出血したりする症状が現れるのです。
また、間食が多かったり、甘い飲み物を頻繁に摂取したりする習慣があると、口腔内に糖分が残り、細菌の繁殖を助長しやすくなります。これも不潔性歯肉炎のリスクを高める要因です。
萌出性歯肉炎
萌出(ほうしゅつ)性歯肉炎とは、子どもの乳歯や永久歯が生え始める際、歯が歯ぐきを押し広げることによって起こる炎症です。歯の萌出時期には、歯ぐきが一時的に腫れたり赤くなったりすることがあり、場合によっては痛みや出血を伴うこともあります。
萌出性歯肉炎は、生え変わりの影響で起こる一過性の炎症のため、自然に治まることも多いです。
しかし、口腔内の衛生状態が悪いと、炎症が長引いたり、細菌感染によって化膿するリスクが高まります。特に、生えかけの歯の周囲は歯ブラシが届きにくく、プラークがたまりやすいため、丁寧なブラッシングが重要です。
若年性歯肉炎
若年性歯肉炎は、10代頃の子どもに見られることが多く、急速に進行する歯肉炎です。基本的にはプラークの蓄積が主な原因ですが、不潔性歯肉炎よりも炎症が強く現れるケースが多いです。
歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなったりするのが特徴です。歯の動揺が見られる場合や、歯肉の下に膿がたまるケースもあり、放置すると歯を支える骨にまで影響が及ぶこともあります。
思春期性歯肉炎
思春期に入ると、ホルモンバランスの変化により歯ぐきが一時的に敏感になりやすくなります。これにより、プラークに対する免疫反応が強まり、炎症が起こるのが思春期性歯肉炎です。
特に、中学生前後の年齢に多く見られ、腫れや出血が顕著に現れることもあります。成長に伴って自然に改善する場合もありますが、口腔ケアを怠ると慢性化するおそれもあるため注意が必要です。
歯肉炎を放置するリスク
歯肉炎を放置すると、さまざまなリスクが伴います。子どもの場合でも、早期に適切な対処をしなければ将来的な口腔トラブルの原因になるため注意が必要です。
症状の悪化
歯肉炎が長期間放置されると、炎症が歯ぐきの奥深くまで進行し、歯を支える骨や歯根膜といった組織にまで影響を及ぼします。歯ぐきが下がって歯が長く見えるようになったり、歯と歯の間にすき間ができたりします。
さらに進行すると、歯のグラつきが出て、最終的には自然に抜け落ちることもあります。子どもの永久歯がこのような状態になれば、将来的に入れ歯やインプラントといった処置が必要になる可能性も否定できません。
全身の健康にも影響が及ぶ
歯肉炎は、口の中だけの問題にとどまらず、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがあるといわれています。炎症によって発生する細菌やその毒素が血流に乗って体内を巡ることで、心疾患や糖尿病などの慢性疾患を悪化させるリスクがあるのです。
学業や生活への影響
歯肉炎を放置して痛みが出るようになると、子どもは食事や会話に支障をきたします。それだけでなく、集中力の低下や睡眠の質の悪化といった二次的な問題にもつながることがあります。
食事をしっかり取れなくなれば栄養状態にも影響し、成長に必要なエネルギーや栄養素が不足することも考えられます。さらに、口臭が強くなることで人間関係に悩みを抱えるケースもあるため、心身の健やかな発育を守るためにも、歯肉炎の早期対応は非常に大切です。
子どもが歯肉炎になったときの対処方法
子どもに歯ぐきの腫れや出血といった歯肉炎の症状が見られた場合、まずは歯科医院を受診しましょう。専門の診断を受けることで、炎症の程度や原因を正確に把握し、適切な治療計画を立ててもらえます。
多くの場合、歯肉炎は歯ぐき周辺のプラークや歯石が原因となっているため、歯科でのプロフェッショナルクリーニングが効果的です。
また、口腔ケアの方法を一緒に見直すことも必要です。生え変わりの時期などは特に、口内環境が激しく変化するため、適切なブラッシング方法も変化していきます。
お子さまのお口の中の状態をよく確認しながら、しっかりと歯磨きすることが求められます。
子どもが歯肉炎になるのを防ぐためには
ここでは、子どもが歯肉炎にならないために家庭でできる予防策について解説します。
正しい歯磨き習慣を身につける
歯肉炎を防ぐ基本は、丁寧な歯磨きです。特に子どもの場合、磨き残しが多くなりやすく、歯と歯ぐきの境目にプラークが蓄積しやすくなります。
プラークが細菌の温床となり、炎症の原因となります。小学3〜4年生頃までは、保護者の方が仕上げ磨きをしてあげましょう。歯ぐきに優しくブラシが当たるよう意識し、磨く強さや角度にも注意を払うことで、炎症の発症を防げます。
食生活の工夫でリスクを減らす
虫歯と同様に、歯肉炎も食生活が大きく関係します。糖分を多く含むお菓子やジュースの摂りすぎは、プラークの増加を招き、炎症を引き起こしやすくなります。
間食の回数を必要最低限に抑え、甘いものを食べた後は早めに歯をみがく、または口をゆすぐといった習慣を身につけると良いでしょう。
また、野菜や果物、歯ごたえのある食材を積極的に取り入れることで、咀嚼によって唾液の分泌が促進され、口内の自浄作用が高まります。さらに、カルシウムやビタミンCといった栄養素は歯ぐきの健康維持に役立つため、バランスの良い食事が重要です。
定期的に歯科検診を受ける
どれだけ家庭でのケアを徹底していても、すべての汚れを完全に取り除くのは難しいです。そのため、定期的に歯科医院でプロのチェックを受けることが、歯肉炎予防には欠かせません。歯科医院では歯ぐきの状態を正確に診断し、必要に応じてクリーニングやフッ素塗布を行ってもらえます。
生活リズムの安定と心のサポート
見落とされることが多いのが、生活習慣の乱れによる免疫力の低下です。夜更かしや栄養の偏り、ストレスなどが続くと、身体の抵抗力が落ちて口内の細菌が増殖しやすくなり、歯ぐきの炎症につながることがあります。
子どもの歯肉炎を防ぐためには、規則正しい生活リズムを整え、しっかりと睡眠を取らせることも大切です。
患者様の声
ここでは、当院に通われている患者様のお声をご紹介します。
口コミ①
怖がりの子どもがお世話になっています。女性の先生にいつも診察していただきますが、子どもにどのような治療を行うか優しく説明をし、子どもに確認をしながら治療をしてくださるので、子ども自身も安心して治療を受けています。
治療中とても誉めてくださるので、とても嬉しいようです。今では自分から「歯医者さんに行きたい」と言って予約をせがまれる程大好きです。歯科衛生士さんや受付の方もとても親切です。
口コミ②
先生方も受付の方も皆様丁寧で気持ちよく通わせていただいております。子どもも行くのを嫌がらないので助かります。
まとめ
子どもの歯肉炎は見逃されやすいものの、放置すると歯周病へ進行し、将来的に歯を失うリスクもある深刻な問題です。主な原因は磨き残しによるプラークの蓄積で、正しい歯磨きや食生活の見直し、定期的な歯科受診が予防には欠かせません。
特に、思春期はホルモンの影響で歯ぐきが敏感になるため、より注意が必要です。
症状が出た場合は、早めに歯科医院を受診し、適切な治療と日常のケアを見直すことが重要です。家庭でのサポートと習慣づけが、子どもの健やかな口腔環境を守るために欠かせません。
お子さまの歯肉炎の治療を検討されている方は、兵庫県宝塚市にある医療法人社団 宝塚ライフ歯科・矯正歯科にご相談ください。
当院は、0歳から100歳まで家族みんなで安心して通える歯医者を目指して診療を行っています。小児矯正・小児歯科や成人矯正、虫歯・歯周病治療やマタニティ歯科など、さまざまな分野に力を入れています。
当院のホームページはこちら、WEB予約・LINEの予約相談なども受け付けておりますので、ぜひご覧ください。
奥村亮司